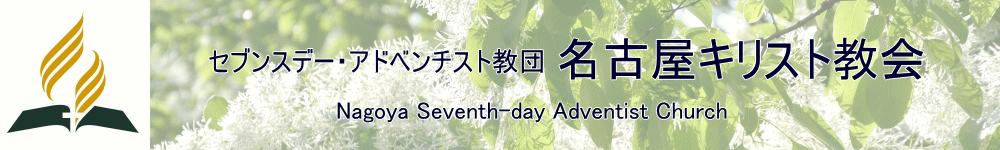
| 2025年安息日学校ガイド第2期 「聖書の預言の学び方」 |
2025年2期1課 「預言のいくつかの原則」
【今週のテーマ】
今週は、預言を学ぶにあたって知っておくべきいくつかの重要な原則を学びます。
【日・読者は悟れ】
世界中で、聖書ほど読まれている書物はありません。多くの人を励まし、力づけ、希望を与え続けてきました。ところが、興味深いことに、同じみ言葉でも、読む人によって、そこから感じることや理解が異なることが少なくありません。特に、預言はその傾向が強く、様々な解釈が生まれたり、そのことが、しばしば混乱の元となったりします。確かに、その人の理解力や信仰の度合いによって、受ける印象や感じ方が異なることもあるでしょう。しかし、聖書は生きた神の言葉であり、真理です。真理とはただ一つの永遠に変わることのないものです。ですから、本来、いくつもの解釈が生まれるべきではないのです。聖書は、「読者は悟れ」(マタイ24:15)と言います。私達は聖書を学ぶにあたって、聖霊の助けを祈り求め、真理に目が開かれて、正しい悟りへと導かれるようにと祈る求める謙虚な姿勢がまず大切です。そして、「この預言の言葉を朗読する人と、これを聞いて、中に記されたことを守る人たちとは幸いである」(黙示録1:3)とあるように、ただ読むだけでなく、実際に、そのみ言葉を守るとき、換言すれば、み言葉に生きるときに、より一層、真理が明らかになるのです。
【月・神は理解されることを望まれる】
イザヤ55:9 「天が地を高く超えているように、わたしの道はあなたたちの道を、わたしの思いはあなたたちの思いを、高く超えている」
神様の思いは私達の思いを遥かに高く超えています。このことは、私達が神様を完全に理解することはできないということでもあります。実際、「その驚くべき知識はわたしを超え、あまりにも高くて到達できない」(詩編139:6)とか、「ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。だれが、神の定めを究め尽くし、神の道を理解し尽くせよう」(ローマ11:33)など、無限の神様を知ることの人間の限界が語られています。ならば、どうして神様のみ言葉を悟ることができると言えるのでしょうか。神様のすべてを理解することはできませんが、私達の救いに関して必要なことは理解できるのです。
テモテ第二3:15
「…この書物は、キリスト・イエスへの信仰を通して救いに導く知恵を、あなたに与えることができます。
預言についても、その重要な目的の一つは、救済計画の説明や、その備えをさせることであると推測できます。それゆえ、難解と思われる預言も、理解不可能というわけではないのです。
【火・ダニエル―これらのことを秘めなさい】
ダニエルは異国の地で捕囚の身にありながら、神様から終末の預言を示された預言者です。12章において、「その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ちあがり…地のちりの中に眠っている者のうち、多くの者は目をさますでしょう」(ダニエル12:1,2)と、終末のクライマックスについて示されるのですが、「ダニエルよ、終わりの時が来るまで、お前はこれらのことを秘め、この書を封じておきなさい」(ダニエル書12:4)と言われるのです。これはおそらく、ダニエルの時代の人々が聞いても、理解できなかったからでしょう。ダニエル自身、「わたしはこれを聞いたけれども悟れなかった」(ダニエル12:8)と言っています。しかし、「知識は増す。」(ダニエル書12:4)と、主は続けられました。つまり、今はわからなくても、やがて知識が増してダニエル書で語られた預言が理解できるときが来るということです。長い歴史の中で様々な時期に、様々な方法で、多くの預言者を通して語られた終わりの時に関する預言が、まるでパズルゲームのように一つひとつのピースを組み合わされて、全体像が見えてくる。最後のパズルのピースは黙示録の中にあります。それゆえ、黙示録22:10で、「この書物の預言の言葉を、秘密にしておいてはいけない。時が迫っているからである」と、主は語られたのです。エレン・ホワイトはとても印象的な言葉を残しています。
「黙示録において聖書のすべての書が出会い、そして終わる。これはダニエル書を補って完成させるものである。」患難から栄光へ下P290
セブンスデー・アドベンチスト教会は、まさにこの預言が成就する形で、すなわち、ダニエル書の理解が深まり、目が開かれて生まれました。この自覚のゆえ、預言の民と自負しているわけです。
【水・御言葉を研究する】
イエス様は、「はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない」(マタイ5:18)と言われました。天地は消え失せるときが来るのに、み言葉は最後まで、「一点一画も消え去ることはない」のです。それほど絶大な価値があり、私達が何よりも先んじて研究すべきものであることがわかります。また、聖書は、「キリスト・イエスへの信仰を通して救いに導く知恵を、あなたに与えることができます」(テモテ二3:15)。「聖書は…人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練」(テモテ二3:16)をするとあります。さらに、何よりも、イエス様は「聖書全体にわたり、御自分について書かれていること」(ルカ24:27)を説明されました。それが預言の研究であったとしても、それは興味本位に未来を探るようなものではなく、その人を救いに導く知恵を与え、教え、戒め、誤りを正し、義に導き、最終的にキリストに至るものとなり、そこに預言が書かれた意味があるのです。
【木・比喩的か、文字どおりか】
聖書の言葉は、文字どおりに受け取る場合と、比喩的に受け取る場合があります。こと預言においては比喩が用いられることが多いのですが、文字通りとらえて、無理やり現代の何かに結びつけようとする人も少なくありません。それが文字通りなのか、それとも比喩なのかを判断する一つの方法は、聖書全体を通して、他にどのように使われているかを確認することです。たとえば、「角」です。ダニエル7:7に十本の角を持つ第四の獣が登場しますが、同24節を見ると、「十の角はこの国に立つ十人の王」であると解説されています。つまり、「角」が政治的権力や国家を表していることがわかります。他の箇所で「角」が出てきた場合、同じようにそれは政治的権力や国家を表わしていると理解するわけです。また、「剣」は神の言葉を象徴しています。(エフェソ6:17「霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい」)。黙示録1:16に、「右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった」とキリストが描写されていますが、「口からは鋭い両刃の剣が出て」いる姿に違和感を持つ人も少なくないことでしょう。しかし、口から鋭いみ言葉が発せられているお姿を想像すれば、違和感も解消されます。この他にも、黙示録にたくさん出てくる「女」は、教会を象徴しています(エフェソ5:31,32参照)。「携挙」を信じる人たちの主張の1つとして、黙示録のある時点から「教会」という言葉が出てこないから、その時点で天に携挙されているのだと理解します。しかし、「女」という象徴を使って教会は出てくるのです。なぜ、比喩や象徴を用いてしばしば聖書が語られるのか、すべてのことはわかりませんが、このことの中に神様の知恵があるのは確かで、この原則に従って預言を解釈していくことが重要です。
(C)2010 NAGOYA SDA CHURCH