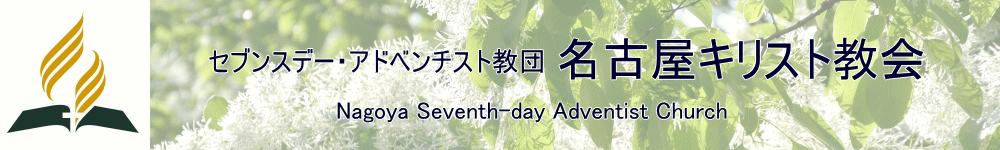
| 2025年安息日学校ガイド第2期 「聖書の預言の学び方」 |
2025年2期9課 「詩篇における例その2」
【今週のテーマ】
先週に引き続き今週も、詩編から黙示録を学んでいきます。
【日・苦難の時の助け】
「私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ、沸き返り、その高ぶるさまに山々が震えるとも・・・」詩編46編3~5節
詩編46編は、多くの試練や困難の中にあっても、神様がその中にあって神の民を守り助けて下さることを力強く歌っています。しかし、そこに描かれた試練や困難は、通常の試練や困難ではなく、「地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも」などと表現されており、これはまるで、この世の終わりを連想させるものとなっており、黙示録6章14節の「天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も、みなその場所から移された」という、再臨直前の預言とも似ています。しかし、詩篇46編はそのような絶望的な状況の中で、「夜明けとともに、神は助けをお与えになる」(6節)「万軍の主はわたしたちと共にいます。ヤコブの神はわたしたちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう」(8~10節)と語っています。この時、私たちに求められていることは、「力を捨てよ、知れ。わたしは神。国々にあがめられ、この地であがめられる」(11節)ということです。
【月・混乱の中の希望】
詩編46編は、地球がキリストの再臨によって物理的に大きな影響を受けることを示しており、これは象徴ではなく、実際に起こると思われます。エレミヤ4:23~26にかけても、次のように記されています。
「わたしは見た。見よ、大地は混沌とし空には光がなかった。わたしは見た。見よ、山は揺れ動きすべての丘は震えていた。わたしは見た。見よ、人はうせ空の鳥はことごとく逃げ去っていた。わたしは見た。見よ、実り豊かな地は荒れ野に変わり、町々はことごとく、主の御前に、主の激しい怒りによって打ち倒されていた。」
突如起きる天変地異は、当然人間も巻き込まれていくことになります。エレミヤは「人はうせてしまう」と述べていますが、それがいかに深刻な状況であるかを物語っています。また、ダニエルは「ある夜、わたしは幻を見た。見よ、天の四方から風が起こって、大海を波立たせた。すると、その海から四頭の大きな獣が現れた」(ダニエル7:2、3)と、この地上に次々に起こる国々を幻のうちに見せられますが、「大波」とか「獣」と表現されているように、それがどれほど力強くあっても、混乱と争いの中で維持されていくことがわかります。つまり、神の民にとって安住の地ではないということです。しかし、ダニエルが見た幻には続きがありました。それはそのような地上の混乱と争いのさなか、「なお見ていると、王座が据えられ、「日の老いたる者」がそこに座し…裁き主は席に着き巻物が繰り広げられた。」(ダニエル7:9,10)というのです。これは神の裁きの光景です。神は地上で起きることに関して、黙って見過ごされるのではなく、正しく裁かれます。そして、ダニエルがなお見ていると、「見よ、「人の子」のような者が天の雲に乗り、「日の老いたる者」の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた」(ダニエル7:13、14)のです。どれほど地上が混乱と争い、大きな自然災害に巻き込まれようとも、逆にそれは神の裁きの時が来ていることを意味し、最後には、真の永遠の王国を建てられて、私たちはそこに入っていくのです。混乱の中に確かな希望があること覚えましょう。
【火・彼の足もとに】
古代において、足は所有権をあらわすために用いられました。神がアブラハムに、「さあ、この土地を縦横に歩き回るがよい。わたしはそれをあなたに与えるから」(創13:17)と言われたのは、これをよく表しています。ところで、ヨブ記の天の会議にサタンが現れた時、サタンは「地上を巡回し、ほうぼうを歩きまわっていた』と神に向かって言いますが(ヨブ1:7)。これはサタンが、この世界の「所有権」が自分にあることを宣言したということです。確かに、世界で起こることは、神の愛と義が支配する世界では、起こりえないようなことばかりです。人間が神に逆らい、サタンに従った結果、この世界に対するサタンの支配を招いてしまったのです。しかし、やがてこれが覆される時が来ます。詩篇47編4,5節に、「主はいと高き神、畏るべき方、全地に君臨される偉大な王。諸国の民を我らに従わせると宣言し、国々を我らの足もとに置かれた」と書かれてあります。「国々を我らの足もとに置かれた」とは、この世界の所有権が神のもとに戻ることを表しています。では、これはいつ起こるのでしょうか。主が再臨されるときの光景について、テサロニケ一4:16、17にこう書かれています。「すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主御自身が天から降って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから、わたしたち生き残っている者が、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして、わたしたちはいつまでも主と共にいることになります」。私たち地上ではなく空中で主とお会いし、そのまま天に引き上げられていきます。つまり、再臨のときに主が足で地を踏み、その所有権を表すことはないということです。ところが、ゼカリヤ14:4では、「その日、主は御足をもってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は東と西に半分に裂け非常に大きな谷ができる。山の半分は北に退き、半分は南に退く」とあり、こちらでは主が足で地を踏とあります。オリーブ山は主が昇天されですが、これは千年紀のあと、この地が一新した時の事を言っているのです。こうして新天新地においてキリストの王国が再スタートするのです。
【水・ぶどう酒と血】
詩編75編も、「地はそこに住むすべてのものと共に溶け去ろうとしている」(4節)と、世の終わりを思わせる言葉で始まっています。このとき公平な裁きを行う主は、「おごるな。角を高くそびやかすな。胸を張って断言するな」(5,6節)と言われます。そして、「わたしは逆らう者の角をことごとく折り、従う者の角を高く上げる」(11節)と言われます。終わりの日、高慢なものを主は裁かれるということです。常に私たちはこの点を注意していなければなりません。キリストが私たちを救うためにとられた方法は、どこまでもへりくだり、その命まで捧げて下さったことでした。このキリストの心が終わりの日、聖徒たちの心となっていなければならないのです。ところで、聖餐式において、私たちはそのキリストが流された血を象徴するぶどう酒をいただきます。言い換えれば、それは神の命の象徴です。方や、獣の刻印を受ける者は、「神の怒りのぶどう酒を飲むことになり」(黙示録14:10)ます。何という対比でしょうか。しかし、謙遜な心で、主と共に生きることは簡単なことではありません。それゆえ、黙示録14: 12において、「ここに、神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である」と忍耐が強調されているのです。現代人は忍耐することが苦手です。だからこそ逆に、忍耐が求められるのかもしれません。忍耐はやがて信仰、そして唯一無二の希望を生み出すのです。
【木・御救いをすべての民が知るために】
詩編67編は、「神が…御顔の輝きをわたしたちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知…るために」(詩編67:2、3)という神への呼びかけで始まっています。救済計画において、神は、罪人が神の栄光によって滅ぼされることなく、イエス・キリストを通して、その御前に再び近づける道を備えられました。しかし、多くの人々がそれを知らずに生きています。ゆえに、ここに私たちアドベンチストの使命があるのです。キリストを通して神に近づける道が備えられていることを知らせる使命です。それを知らずに、「獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける」(黙示録14:9)ことになれば、神の御顔を仰ぐことができないばかりか、昼も夜も安らぐことがなくなり、最後には神の怒りの杯を混ぜ物なしに飲むことになるのです(黙示録14:10,11)。恐ろしい表現ですが、そうならないために、三人の天使は大きな声で私たちが伝えるべきメッセージを語っているのです。
(C)2010 NAGOYA SDA CHURCH