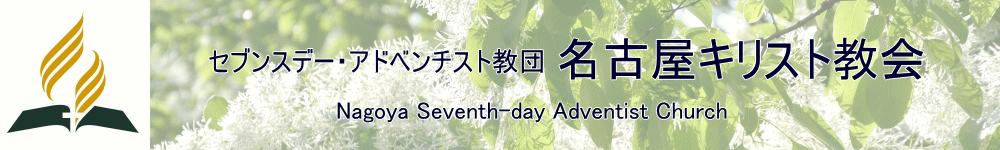
| 2025年安息日学校ガイド第3期 「聖書の預言の学び方」 |
2025年3期13課「幕 屋」
【今週のテーマ】
今週は、幕屋建設について学びます。その意味を知るとき、私達は主の深いご計画と私達に対する思いを知ることでしょう。
【日・主の安息日】
出エジプト記35~40章は、25~31章で示された幕屋建設の再指示となっています。何故同じ内容が繰り返されているのかと言えば、民たちが金の子牛を作って背信した(32章)からです。主から滅ぼすとまで言われた民でしたが、モーセのとりなしにより、その罪が赦され、再び幕屋を作るように指示されたというわけです。幕屋建設に先立ち、主は安息日を聖別することを命じられます。安息日に仕事をするものは死刑に処せられると言われるほど、厳しく戒められました。霊的な意味においては、安息日を聖別し、主を礼拝しない者は、霊の命を失うということです。幕屋建設という神様のための働きであっても、安息日にはそれを中断し、何もしてはならないのでした。安息日を遵守することは、すべてのことに先立って守るべき重要な掟なのです。学生時代、タイの山奥に教会を建てに行ったことがありました。教会を建てるというのは本当に喜びに満ちた尊い聖なる働きでした。しかし、安息日は造りかけの教会をそのままにし、神様に礼拝する時を持ちました。静まって神を礼拝する時間は、教会建設とは違う、霊的力をいただく時間でした。そして、それは翌日からの教会建設のための力ともなっていきました。日常生活において、たとえそれが神様のための働きであったとしても、安息日という静まって神を礼拝する日の大切さを実感しました。私達は、今一度、安息日の守り方について吟味する必要があるかもしれません。また、安息日は日の聖別、聖所は建物の聖別ですが、いずれも、私達の生活の中に神が臨在されることを指し示すものでした。
【月・献げ物と聖霊】
幕屋を建設するためには、金、銀、青銅、上質の亜麻布、宝石など、様々な多くの材料が必要でした。主は、「あなたたちの持ち物のうちから、主のもとに献納物を持って来なさい。すべて進んで心からささげようとする者は、それを主への献納物として携えなさい」(35章5節)と言われました。主への捧げものは、喜んで捧げるその心が大切で、義務感から捧げたり、見栄で捧げるようなものではありません。この主の言葉に対して、多くの民が喜んで、しかも惜しみなく献げたので、有り余るほどとなりました。この貴重な捧げものを用いて、職人たちが幕屋を作り上げていきましたが、その際に、モーセは、ウリの子ベツァルエルを呼び、「彼に神の霊を満たし、どのような工芸にも知恵と英知と知識を持たせ(た)…」(35章31節)と書かれてあります。人が聖霊に満たされるという最初の聖書の記事であることは、すでに学びましたが、神の幕屋は、神の指示通りに完璧に造っていかなければなりません。そのための技術、知恵、芸術的知識を神の霊を通して主は授けられたということです。
【火・建設された幕屋】
出エジプト記36章から39章にかけて、シナイ山で受けた指示に従って行った幕屋の建設について書かれています。具体的には、(1)さまざまな織物、幕、部品などを伴う幕屋(出36:8~38)、(2)掟の箱(同37:1~9)、(3)供えのパンの机(同37:10~16)、(4)燭台(同37:17~24)、(5)香をたく祭壇(同37:25~29)、(6)焼き尽くす献げ物の祭壇(同38:1~7)、(7)手足を洗う洗盤(同38:8)、(8)幕屋を囲む庭(同38:9~20)、
(9)幕屋の建設材料 (同38:21~31)。(10)胸当て、そのほかの祭司の祭服などです。聖所と庭を境に一辺約50mの正方形とならうように、サイズも正確でなければなりませんでした。また幕屋(聖所)では、1年を通じて、二つの異なる儀式が行われました。一つは、日ごとの儀式であり、もう一つは年ごとの儀式です。日ごとの儀式では日ごとの罪の悔い改めと赦しを、年ごとの儀式では民全体の罪の除去と清めを表しており、前者はキリストの十字架の贖いを、後者は天の聖所でのとりなし(再臨前審判)を表していました。
【水・幕屋における神の臨在】
出エジプト記の最終章(40章)は、幕屋と十戒の奉献について書かれてあります。第二年目の第一の月の一日に幕屋が組み立てられ、すべての祭具が所定の位置に置かれました。その月の14日、すなわち過越の祭り(出エジプトしてからちょうど一年後)に間に合うことになります。幕屋が組み立てられた時、「雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ち」(40:34)ました。「雲(シェキナー)」は神の臨在の象徴です。幕屋建造の目的は、25章8節にあるように「わたしのための聖なる所を彼らに造らせなさい。わたしは彼らの中に住む」ためです。そのことが一目でわかるように、「旅路にあるときはいつも、昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えた」(40章38節)のでした。イスラエルはこの雲が幕屋から上ったときに旅立ち、雲が動かなければそこにとどまりました。イスラエルの民はいつもその「雲」を見ていなければなりませんでした。出エジプト記はこの言葉をもって終わるのですが、つまりそれは、主はいつも民の中心におられることを教えているわけです。ここが重要なのです。
【木・人間の間に宿られたイエス】
「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。わたしたちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた」(ヨハネ1:14)
イエス様が人として地上に来られたことを、ヨハネは、「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」と表現しました。この宿られたという言葉の直訳は、幕屋を張ったと言う言葉です。イスラエルの民の中心に幕屋を張り、いつも共におられることを示された主は、同じように、人として地上に来られたとき、そのことを幕屋を張ったと表現して、いつも共におられることを示されたのでした。マタイ1:23では、「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」この名は、「神は我々と共におられる」という意味である」とあり、神と人とがいかに近しい関係にあるかを教えています。そして、やがて私達が天の御国に帰っていく日、「見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となる。神自ら人と共にいて、その神とな(ってくださる)」(黙21:3)のです。新天新地には幕屋はありません。なぜなら、都全体が神殿、神の聖所だからです(同21:22)。
(C)2010 NAGOYA SDA CHURCH