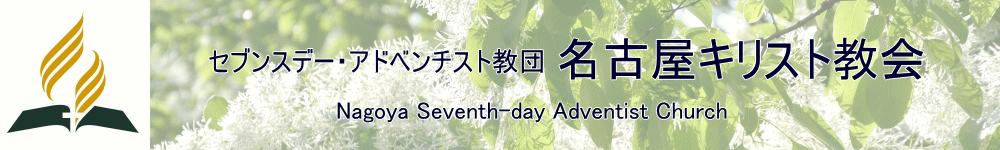
| 2025年安息日学校ガイド第2期 「聖書の預言の学び方」 |
2025年3期7課「命のパンと水」
【今週のテーマ】
今週は、神がイスラエルの民たちを、荒野の生活において、天からマナを降らせ、また岩から水を噴き出させて養い続けて下さったことを学びます。そして、これら一つひとつの経験は、終わりの時代に生きる者たちへの教訓となっていることを学びます。
【日・苦い水】
葦の海をわたった三日後に、問題が起こりました。それは水がないということでした。水があっても苦くて飲めませんでした。そこで民はモーセに向かって、「何を飲んだらよいのか」と不平を言います(出エジプト15章24節)。この言葉自体、それほど酷い不平の言葉には感じないかもしれません。しかし、不都合なことが生じると、なんでもモーセに責任を押し付ける態度は、その背後におられる神に対して文句を言っているのと同じです。三日前に、海の水をわかち、その間を通るという想像を絶するような神の奇跡を経験していたにも関わらず、民たちは今度は自分たちでも神に祈り求めようとはならず、指導者であるモーセに文句を言うだけなのです。長い奴隷生活の中で彼らは卑屈になり、否定的で、すぐに不平不満を口にすることでストレスを発散させるということが常態化していたのでしょう。しかし、今や彼らは奴隷から完全に解放され、神の民として生きようとしていたのです。神は彼らを訓練し、忍耐と従順を学ばせる必要がありました。主はモーセに一本の木を示され、その木を水に投げ込むように言います。すると、苦かった水が甘くなったのです。エジプトを出て二回目の奇跡です。さらに主は、「もしあなたが、あなたの神、主の声に必ず聞き従い、彼の目にかなう正しいことを行い、彼の命令に耳を傾け、すべての掟を守るならば、わたしがエジプト人に下した病をあなたには下さない。わたしはあなたをいやす主である。」(出エジプト記15章26節)と、過酷な生活環境であったとしても、常に健康が守られることを約束してくださったのでした。このような不平ばかりの民であるにもかかわらず、主は彼らを愛し、守って下さるのです。
【月・ウズラとマナ】
水の奇跡を経験したあとも、相変わらず民たちは文句ばかりでした。今度は食べ物がないと言ってモーセとアロンに向かって不平をぶつけたのでした。しかも、「我々はエジプトの国で、主の手にかかって、死んだ方がましだった」(出エジプト16:3)とさえ言う始末です。これは主がこれまでしてくださったことを否定する言葉です。不平不満を言うのが当たり前になってしまうと、主の恵みが見えなくなり、主に対する感謝の心も失ってしまうようです。しかし、神は忍耐をもって民の不平を聞かれます。神は天からマナを降らせ、どこからともなくウズラも現れて、民の飢えを満たしたのでした。ところで、このマナに関しては、不思議な現象が伴いました。それは先の分まで取り置きしても、次の日には腐って食べられなくなってしまうのに、金曜日だけは次の日の分まで与えられ、腐ることもなかったことです。このことを通し、主は、第七日安息日の休みを与えて下さったのです。この現象は40年間荒野にいる間、ずっと続きました。興味深いのは、最初にマナが与えられたのは、まだ十戒が与えられる前だったことです。つまり、十戒は安息日を含めて、明文化されたときからスタートしたのではなく、それは天地万物が創造されたときから、いや、永遠の昔から、変わることのない神の愛なのです。
【火・岩から出た水】
民たちはスエズ湾沿いのシンの荒野から、シナイ山に向けて旅立ち、レフィディムに宿営したとき、再び水がないという問題に直面します。民にしてみれば、自分たちで行先を決めたわけではなく、雲の柱、火の柱に導かれるままに、つまり、主に導かれるままにやってきたのに、なぜ、主は水がなくなるという、命に関わるような問題に、次から次へと直面させるのかと思ったことでしょう。神に従うならば祝福されると多くの人は考えます。しかし、現実はそうならないことも少なくないのです。さて、私たちはこれをどう理解したら良いのでしょうか。キリストは、「だから、『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思い悩むな」(マタイ6章31節)と言われました。そして、「何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはみな加えて与えられる。」(マタイ6章33節)と続けられました。このことを、イスラエルの民に教えようとされていたのかもしれません。しかし、彼らがそれを真に理解するには、まだまだ時間と経験が必要でした。主はモーセに、ホレブの岩を打てと言われました。モーセは、長老たちの目の前でそのとおりにすると、岩から水が噴き出したのでした。この岩はキリストを表していました。
「皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは、自分たちに離れずについて来た霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです」(コリント一10章4節)
つまり、人々は主をうちたたき、命の水を飲むことができ、主は打たれた傷によって民を癒されたのです。
【水・エトロ】
18章に、モーセのしゅうとで、ミディアンの祭司であったエトロが、神がモーセとその民イスラエルのためになされたことを聞いて、実家に戻ってきていた妻のツィポラと二人の息子を連れてやってきたことが書かれています。途中まで一緒だった妻と子供たちを、いつ実家に帰したのかは書かれていませんが、久しぶりの再会に、モーセもどれほどうれしかったことでしょう。このとき、エトロは大群衆の様々な相談を聞き、一人で問題に対処しているモーセを見て、「あなたは、民全員の中から、神を畏れる有能な人で、不正な利得を憎み、信頼に値する人物を選び、千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長として民の上に立てなさい。平素は彼らに民を裁かせ、大きな事件があったときだけ、あなたのもとに持って来させ(なさい)」(18章21、22節)とアドバイスします。どれほど偉大な人でも、一人で何もかもはできません。そう考えること自体、傲慢です。他の人にゆだねていくことは、自分の助けになるだけでなく、その人を育てることでもあります。また、このような組織化は、現代の教会組織や小グループにおいても、助けとなります。
【木・命のパンと水】
後に、パウロは出エジプトの出来事が克明に残されている理由について、次のように述べています。「これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面しているわたしたちに警告するためなのです」(コリント一10章11節)。その中でも、パウロが強調したのは、「あなたがたはそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は、滅ぼす者に滅ぼされました」(同10節)ということでした。不平を言いたくなることがあったなら、毎日イスラエルの民にマナを降らせ、岩から水を出させたように、神が日ごとに必要な命のパンと水を与えて下さっていることを思い返すことです。命とパンと水、それはイエスキリストご自身を与えて下さっているということです。イエス様は「渇くものは私のもとに来て飲むが良い」(ヨハネ7:37)と言われました。また、ご自分のことを、「わたしは命のパンである」(ヨハネ6:31)と言われました。日々の生活の中で困難や理解できないことがあったとしても、主は、私たちの霊的な命を、永遠の命をいつも、支えて下さっているのです。
(C)2010 NAGOYA SDA CHURCH