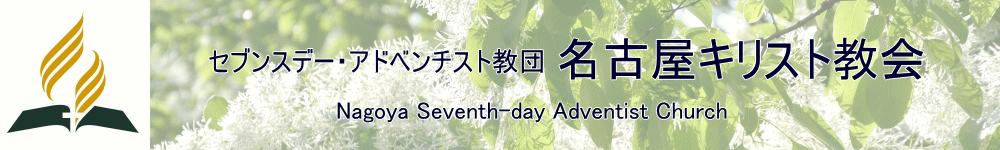
| 2025年安息日学校ガイド第2期 「聖書の預言の学び方」 |
2025年3期9課「律法を実践する」
【今週のテーマ】
今週は、十戒が与えられた後に、より具体的に律法を実践するために与えられた契約の書について学びます。
【日・契約の書】
シナイで律法(十戒)が与えられたあと、「契約の書」が与えられます。これは律法の原則を日常生活に適用されるためのものですが、民たちは、奴隷生活と偶像礼拝によって盲目になり、堕落していたので、神の10の戒めの深遠な原則を十分に理解する備えができていなかったのです。そこで、「契約の書」を通して、十戒の義務を十分に理解し、励行するために、十戒の原則を適用するための追加的な戒めが与えられたのでした。「契約の書」は、いくつかの章に分かれて記されていますが、大まかに分類すると、21章は、生命に関して、22章は、道徳に関して、23章は、礼拝、祭り事に関して記されています。最初に、奴隷制度に関して出てきますが、当時の奴隷制度は、現代や中世の悪質で邪悪な奴隷制度とは異なります。ヘブライ人の奴隷は、保護され、大切にされていました。たとえば、奴隷期間が6年間に制限され(出21:1、2、エレ34:8~22)、7年目には、主人のもとにとどまることを望む場合を除き、すべての奴隷が解放されなければなりませんでした。
【月・そのほかの律法】
奴隷制度に続いて、12節~17節までは死刑に処せられる4つの重罪について記されています。具体的には、①故意に人を打って殺した者 ②自分の父母を打つ者 ③人をさらった者 ④父母を呪う者が死刑に処せられる重罪として示されました。18節以降は、死刑には至らない犯罪に関して記されています。一つひとつの犯罪に対して、賠償が詳しく記されているのが特徴です。また、ハンムラビ法典で知られる同害報復法、「命には命、目には目、歯には歯、手には手…」(23~25節)なども出てきます。この契約の書全体を通して注目すべきは、重い犯罪から順に書かれてあるわけですが、最も弱い奴隷についての法律が最初に来ていることです。つまり最も弱い者が優先されているということです。ここに神の愛があります。22章に入ると家畜、性的犯罪、金銭に関する問題が続き、さらに、23章に入ると、安息日や祭り事、正しい礼拝のあり方などについて触れられていきます。
【火・神の当初の計画】
イスラエルの人々は律法を授かった後、これから新しい土地に入っていくことになるわけですが、本来、そのために先住民たちと戦うことは、神の意図ではありませんでした。それは戦うことなしに、彼らに与えられるものでした。新しい土地は、アブラハム、イサク、ヤコブに約束されており、イスラエルに対する神の特別な賜物として受け取られるはずでした。ちょうどそれは、エジプト軍と戦うことなく、脱出できたのと同様です。このことに関して、主は、「見よ、わたしはあなたの前に使いを遣わして、あなたを道で守らせ、わたしの備えた場所に導かせる。あなたは彼に心を留め、その声に聞き従い、彼に逆らってはならない。彼はあなたたちの背きを赦さないであろう。彼はわたしの名を帯びているからである。しかし、もしあなたが彼の声に聞き従い、わたしの語ることをすべて行うならば、わたしはあなたの敵に敵対し、仇に仇を報いる」(23章20~23節)と言われました。主は天使を遣わして民を守り、約束の地に導かれることを約束されたのです。天の軍勢に勝てる人間はいません。主は、単に民を導かれるだけでなく、民の前を行き、前に待ち伏せる敵と戦ってくださる方なのです。これは私たちの人性においても同様です。天から使いが送られて、敵であるサタンや世の誘惑から守られながら、約束の天のカナンに導かれていくのです。そう考えると、なんと心強いことでしょうか。しかし、それには一つ条件があって、それは主に逆らわず、主のみ声に聞き従うことだと言われました。
【水・目には目を】
契約の書の中には、先にも触れた同害報復法と呼ばれるものが出てきます。「命には命、目には目、歯には歯、手には手…」(23~25節)というように、これは、もし他者から何らかの損害を受けた場合、同じ種類の害を加害者に対して行う刑罰のことを言います。ハンムラビ法典などの古代オリエントの法やイスラム法(キサース)など、中東世界には広く、この教えが広がっていました。同害報復法はそのまま読むと、報復を許可しているようにとられがちですが、しかし、その本質は、際限のない復讐をさせないようにするためのものです。しかも、イスラム教などでは、この同害報復の権利をなるべく行使しないようにとも教えられているようです。では、聖書はどうでしょう。御存じの通り、キリストは、「目には目を、歯には歯をと命じられたのを、あなたがたは聞いている。しかしわたしはあなたがたに言う、悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向けなさい」(マタイ5章38節)と教えられ、同害報復をなるべく行使しないようにどころか、明確に禁じています。誰かから損害を受けたとしても、復讐ではなく、相手を赦し、愛をもって答えていくようにと教えています。
【木・復讐】
「愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。『「復讐はわたしのすること、わたしが報復する」と主は言われる』と書いてあります」(ロマ12:19)
現代社会と同様に、聖書は損害を受けた個人が復讐することを禁じています。もし復讐すれば、その人も同じ罪に問われることになります。現代の法治国家においては、犯罪を犯せば、裁判が行われ、その国の法律によって裁きを受けることになります。つまり、自ら復讐せずとも国家が報いを与えるというわけです。古代イスラエルにおいてもそれは同じで、たとえば士師の時代には、13人の士師たちが、「さばきつかさ」となり、様々な犯罪に対して、裁きをつかさどっていました。王政となってからは、王が最終的な裁き主となっていきました。しかし、裁判にならないようなことでも、相手に憎しみを抱いてしまうようなことがあります。裁判になり、社会的正義が行われたとしても、その内容に納得いかないこともあるかもしれません。また、赤穂浪士の物語のように、復讐が美化されることもあります。しかし、聖書は、人に対して抱く悪い感情を、神にゆだねなさいと教えるのです。そして神が代わりに復讐されると言うのです。もちろん、神が目には目、歯には歯をという具合に、私たちの代わりに復讐されるのではありません。その意味は、神が正しい正義を下して下さるということです。その神の正しい裁きにゆだねなさいということが、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさいということなのです。
(C)2010 NAGOYA SDA CHURCH